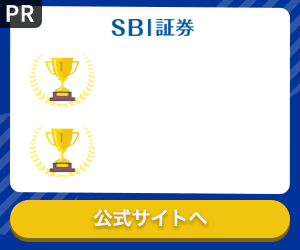「長期で安定した配当を受け取りたい」「高配当株をポートフォリオのコアにしたい」
そんな方に今、静かな注目を集めているのが学究社(GAKKYUSHA)です。首都圏を中心に進学塾「ena」ブランドを展開し、着実な業績と高い配当を維持してきた学究社は、教育関連株の中でも異彩を放つ存在です。
とはいえ、長期保有を考える上では「本当に安定した配当が続くのか」「今後のリスクはないのか」といった疑問や不安もつきもの。そこで本記事では、最新の有価証券報告書をもとに、学究社の事業内容や財務状況、配当の実績、そして長期投資で注意したいリスクまで、分かりやすく解説します。
高配当株としての魅力と、20年・30年と安心して保有できるのか
気になるポイントを徹底チェックしていきましょう。
学究社はどんな会社?高配当株として注目される理由
まずは、学究社がなぜ高配当株として注目されているのか、その土台となる事業内容や企業としての特徴を見ていきましょう。単なる学習塾運営にとどまらない、学究社ならではの強みや独自性が、安定した業績や配当の背景にあります。最初に、学究社の事業内容とその強みについて詳しく解説します。
学究社の事業内容と強み
学究社は、主に首都圏を中心に展開する進学塾「ena」ブランドを柱とした教育事業を展開しています。中学・高校・大学受験を目指す生徒を対象に、集団指導から個別指導、看護・美術など専門分野の受験指導、さらにはオンライン授業や家庭教師サービスまで、幅広いニーズに応える多彩なコースを持っているのが特徴です。
また、教育事業だけでなく、自社保有の不動産を活用した賃貸事業や、インターネットを活用した教育情報配信サービスなどもグループ全体で手がけています。このように、教育を軸にしながらも複数の収益源を持つことで、景気や教育業界の変化にも柔軟に対応できる経営基盤を築いている点は大きな強みです。
特に、学究社は「都立中高一貫校受験」や「難関校合格実績」で高い評価を獲得し、ブランド力を強化してきました。長年にわたるノウハウの蓄積と、首都圏でのドミナント展開による地域密着型の運営体制も、安定成長を支える重要なポイントです。こうした事業の多角化とブランド戦略が、安定した収益と高配当を実現する土台となっています。
売上・利益・財務の推移から見る安定性
学究社の大きな特徴は、売上や利益、そして財務基盤の「安定感」にあります。直近5年間の業績を見ても、売上高は毎年じわじわと増加を続け、2025年3月期には過去最高の約133億円に到達しました。経常利益も一貫して高水準をキープし、純利益も右肩上がりで推移しています。
さらに注目したいのが、自己資本比率の高さです。2025年3月期の自己資本比率は60%を超えており、教育関連株の中でもトップクラスの財務健全性を誇ります。現金および現金同等物も30億円以上と豊富で、有利子負債も少なく、万が一の経済環境の変動にも十分耐えられる体力を持っています。
また、営業キャッシュフローも毎年しっかりと黒字を確保しており、資金繰りの安定度も抜群。新規校舎の開設や設備投資、株主への安定配当など、成長と還元の両立ができている理由は、こうした堅実な財務体質に支えられています。
配当方針と実績~なぜ高配当株として人気なのか
学究社が「高配当株」として注目される背景には、配当政策の安定性と増配傾向、そして株主還元意識の高さがあります。以下に、その実態を具体的に見ていきましょう。
学究社が高配当株として人気を集めている理由は、配当の安定性と株主還元に対する強い姿勢にあります。
まず、配当実績を見てみると、2021年3月期の1株あたり配当65円から、2025年3月期には90円へと増配が続いています(途中の年度で87円の維持もあり)。さらに、配当性向はここ数年50%台半ばと高い水準を保ち、利益の半分以上を安定して株主に還元している点が特徴です。
また、学究社は業績悪化時でも急な減配や無配に転じた例がなく、今後も安定した配当方針が維持される見通しです。株価に対する配当利回りも3~4%台と高水準を維持し、高配当株を重視する長期投資家から支持を集めています。
このような配当の安定感と増配の実績が、学究社を高配当株として評価する大きな理由となっています。
長期保有で気をつけたいポイントとリスク
ここまで、学究社の安定した業績や配当について解説してきましたが、長期保有を考えるなら、今後のリスクにも目を向けることが大切です。どんなに財務や配当が安定していても、業界全体の構造変化や予期せぬ逆風は避けられません。
学究社が属する教育業界には、少子化や競合の増加など、長期的に注視すべきリスクがいくつかあります。まずは、この分野で直面している主な業界リスクについて確認していきましょう。
少子化や競争激化など業界リスク
学究社を長期で保有する際に無視できない最大のリスクが、やはり少子化による市場縮小です。日本全体で子どもの数が減り続けている中、今後は学習塾の生徒数自体が減少する可能性が高くなっています。
また、教育業界は参入障壁が低く、オンライン塾やIT企業、異業種からの新規参入も増加しています。そのため、これまでと同じやり方では競争に勝ち残るのが難しくなる局面も考えられます。
さらに、教育制度の変更や受験制度の見直し、予測不能な社会変化(パンデミックや自然災害など)も業績に影響を与えるリスクです。学究社は首都圏中心のドミナント展開や多角化戦略で対応を進めていますが、長期的にはこれらの環境変化にどう適応できるかが重要なポイントとなります。
人材・ブランド維持への取り組み
教育サービスの品質を維持し続けるためには、優秀な講師やスタッフの確保・育成が不可欠です。学究社も、人材育成や働きやすい環境づくり、多様な採用の強化に力を入れています。実践型研修や管理職への女性登用、働き方改革など、多様な人材が活躍できる体制づくりを推進中です。
また、「ena」ブランドは都立中高一貫校や難関校での高い合格実績を通じて強固な地位を築いてきましたが、ブランド力を維持するには今後も合格実績やサービス品質の向上が不可欠です。オンライン授業や専門分野への対応、私立受験への展開など、多様化する教育ニーズに柔軟に対応する姿勢も見逃せません。
このように、人材とブランドの両面から企業価値を維持・向上させる取り組みが、学究社の持続的な成長のカギとなっています。
財務・配当の長期的な持続可能性
長期保有を考える上で、財務の健全性と配当が将来にわたって維持できるかは非常に重要なポイントです。学究社は自己資本比率60%超、現金や現金等価物も潤沢で、有利子負債も抑えられており、財務基盤は非常に安定しています。
この健全な財務体質があるからこそ、配当性向50%超という高い水準での安定配当を継続できています。営業キャッシュフローも毎年黒字を維持し、設備投資や新規事業への挑戦、株主還元の両立が実現できているのが強みです。
ただし、少子化や業界環境の大きな変化が続く中では、将来的な減配や業績悪化の可能性もゼロではありません。今後も配当方針と財務状況がどのように推移するかを定期的にチェックすることが、長期保有のリスク管理につながります。
本記事のまとめ
- 学究社は首都圏中心の進学塾「ena」ブランドを展開
- 事業は教育を軸に不動産・教育メディアも手がける多角化体制
- 売上・利益ともに過去5年で安定成長を維持
- 自己資本比率60%超で財務の安全性が非常に高い
- 現金・現金同等物も潤沢で倒産リスクが低い
- 1株あたり配当は毎年増配または高水準で推移
- 配当性向50%超、株主還元に積極的
- 配当利回り3~4%台の高配当株として注目
- 少子化による生徒数減少リスクは中長期的に存在
- オンライン塾など新たな競争環境にも直面
- 人材育成や働きやすい環境づくりに積極的
- 高い合格実績とブランド力が集客と業績の支え
- 設備投資・新規出校にも積極的で成長志向あり
- 業界や社会の構造変化リスクにも柔軟に対応中
- 安定配当を重視する長期投資家に向く銘柄









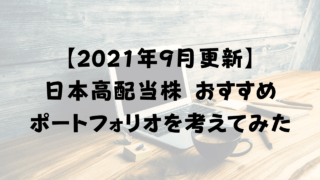




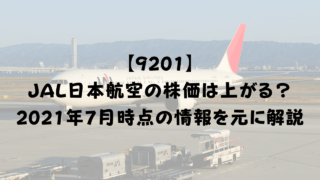





 楽天証券
楽天証券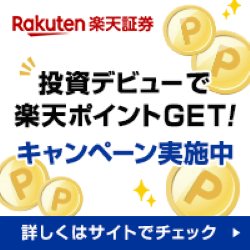
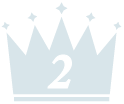 Coincheck
Coincheck
 SBI証券
SBI証券